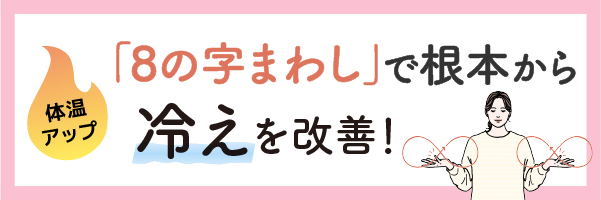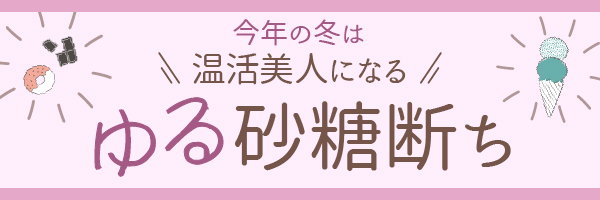長引く咳、息切れは天気のせい?|気象病ドクター久手堅司先生の連載
気象病ドクター・久手堅司先生による連載。季節の変わり目にはぜんそくの症状が強く出たり、冷えからくる不調を感じやすくなります。体を労わるコツや漢方薬の取り入れ方についても紹介します。
目次
秋はぜんそく(気管支喘息)に注意!

ぜんそくは、気圧や気温、湿度の変化が影響する「気象病」でも悪化しやすくなります。秋は、急な冷え込みや天候の不安定さから体が冷えやすく、気道が刺激されて発作が起こりやすい季節です。
また、台風など低気圧のときは自律神経が乱れ、症状が悪化することも。実際に「雨の日になると咳が出やすい」と感じる人も少なくありません。
さらに、秋になると花粉が飛びやすく、空気の乾燥でハウスダストも舞いやすくなります。こうしたアレルゲンの増加が、ぜんそくの症状を引き起こしたり悪化させたりする原因に。
気象の変化とぜんそくの関係とは?

実は、気温や気圧の変化によって、ぜんそくの症状が悪化しやすくなることは以前から知られています。第70回日本アレルギー学会学術大会で発表された『喘息予防·管理ガイドライン 2021』にも関連性が示されています。
ぜんそくは気道に炎症が起こり、空気の通り道が狭くなることで呼吸がしづらくなる病気。健康なときには気にならない程度の気温の変化やちょっとした刺激にも敏感に反応し、発作的な咳や息切れが強く出ることがあります。
ぜんそくの発作では、気管支が狭くなり「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といったぜん鳴(ぜんめい)や呼吸のしづらさが特徴です。
ただし、必ずしもぜん鳴が出るとは限らず、「咳ぜんそく」と言ってアレルギー炎症などにより気道が過敏となり、咳だけが続くこともあります。咳に痰が絡むことはほとんどなく、「コンコン」と乾いた音がします。症状の出方は人それぞれなので、咳が長引くときも注意が必要です。
自律神経の乱れが咳や息切れを招く

ぜんそくの症状は自律神経とも関係しています。自律神経は呼吸や心拍、体温などを調整する重要な働きを担っていますが、気象の変動が、気道の炎症や自律神経のバランスに影響を与え、咳や息切れを起こすことがあると考えられます。
ぜんそくの発作が一日の中で最も起こりやすいのは、就寝中や明け方。体をリラックスさせる副交感神経が優位になる時間帯には気道が収縮するため発作が起きやすくなります。
また、ストレスは自律神経のバランスを乱し、気道の過敏性を高めることで、ぜんそくの症状を悪化させます。特に慢性的にぜんそくを持つ人は、気圧の低下や台風の接近など、天気の変化に敏感で症状が出やすくなる傾向があります。
季節の変わり目、ぜんそくが悪化
天気や季節の変化に敏感な人は、特に、秋口など季節の変わり目に体調を崩しやすくなります。自分の体調の変化に気を配り、必要に応じてクリニックを受診することで、ぜんそくの症状を予防·軽減できます。ここで、実際に、ぜんそくを持つ患者さんのエピソードをご紹介します。

【実録】冷えケアで天気に敏感な体が元気に
ぜんそくや冷えによる不調で他院に通院していた30代の女性。秋の時期、寒暖差で症状が悪化し、ぜんそくの吸入薬やアレルギーの薬などを増やしてもなかなか改善されず。
気象病外来では、これまで使っていたぜんそくの薬を併用しつつ、「真武湯(しんぶとう)」という漢方薬を処方したところ、症状の改善がみられました。
真武湯は体を内側から温める作用があり、複数の生薬が組み合わさることで新陳代謝を高め、ぜんそくが起きにくい体質に整える効果も期待できます。
冷えやむくみが強かったことに着目し、元々使用している薬とは関係のない漢方薬を追加したことが不調改善のカギになりました。
ぜんそくや冷えには漢方を選ぶのも手
ぜんそくや冷えの不調には、真武湯をはじめ、葛根湯(かっこんとう)、麦門冬湯(ばくもんどうとう)、小青竜湯(しょうせいりゅうとう)といった漢方薬を使用することができます。それぞれが、どんな症状に効くのかを解説します。

真武湯(しんぶとう)
疲れやすく、全身に冷えが生じて水分代謝も悪くなりむくみやすい場合に用いられます。かぜが長引いて全身倦怠感があるときに使うことも。
葛根湯(かっこんとう)
かぜの初期症状におすすめの漢方薬。さむけや頭痛、首肩のこわばりに効果が期待でき、体を温めることでかぜを治す力をサポート。さらに、筋肉の緊張をほぐして肩コリや頭痛にも効果的。
麦門冬湯(ばくもんどうとう)
たんがあまり出ず、コンコンと乾いたせきが続くときや、かぜの後にせきだけ残るときに。不足した水分を補い、気管支を潤すことで気管支炎や咽頭炎などの症状を和らげます。
小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
さらさらした鼻水や、せきと一緒にたんが多く出るかぜやアレルギー性鼻炎に使えます。体を温めて巡りを改善しながら、水分バランスを整え、鼻やのどの不快感、せき、たんをケア。
漢方薬は複数の生薬が組み合わさっているため、1つの症状だけでなく、体のあちこちの不調に効果を発揮する特徴があります。
「漢方は体にやさしい」と思われがちですが、漢方薬も「薬」。体質によって副作用が出ることもあるので、市販薬を服用する前には 医師に相談しましょう。
早めの冷え対策でぜんそく、不調を軽減

夏場の内臓からの冷えと違い、秋は寒暖差で全身に冷えが伝わりやすく、特に女性はむくみや生理不順、倦怠感などの不調が出やすい季節です。
体を元気に保つには、運動で体内から熱をつくることが効果的です。さらに、朝晩は首が冷えないようにし、日中もマフラーやアウターをプラスして首元をしっかり守りましょう。日照時間が短くなる時期なので、太陽の光を浴びて体をぽかぽかに。
ちょっとした日常の工夫が不調知らずの体づくりにつながりますよ。
イラスト/Aikoberry

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。…
[ 監修者 ]