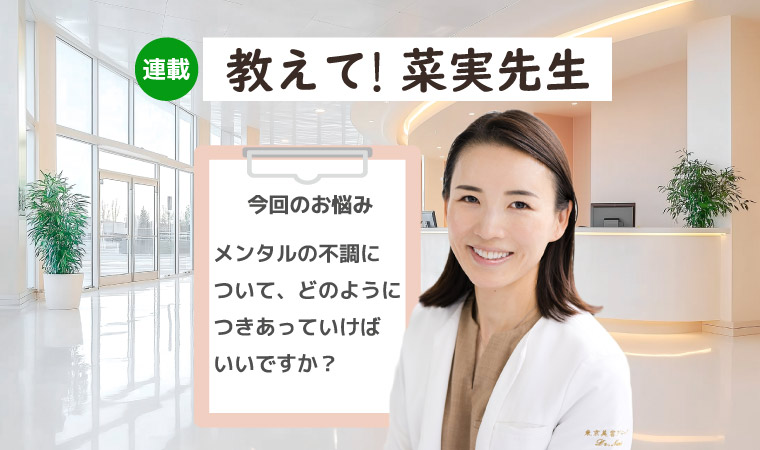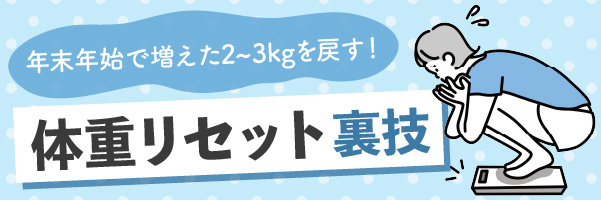「表情のない人」の心理とは?原因と接し方を解説
「周囲に表情のない人がいて何を考えているかわからない」といった経験をしたことがある方もいるでしょう。本記事では、表情のない人の心理や原因、接し方を紹介しているので、気になる方はぜひご覧ください。
目次
「表情のない人」とは?

表情のない人とは、一般的に心情を表情に表すことが少ない人のことを指します。喜怒哀楽など心情の起伏が顔に現れにくいため、周囲からは「何を考えているかわからない」「冷たい」「怒っているのかな?」と誤解を招きやすいのが特徴です。
しかし、表情がないからといって必ずしも心情がないわけではありません。内面では豊かに感情を感じていても、外に表現することが苦手な場合が多い傾向にあります。性格や育った環境、心理的な要因、身体的な理由など、様々な背景によって生じます。
表情のない人は意図的に無表情を装っているわけではなく、その状態が自然であるため、周囲の反応に戸惑うことも少なくありません。
「表情のない人」に見られる特徴

表情が乏しい人は、感情表現が苦手だったり自分に自信がなかったりするのが特徴です。無表情状態を作り出すには、様々な要因が絡み合っています。
ここでは、表情のない人に見られる5つの特徴を紹介します。
感情表現が苦手
表情が乏しい人の最も典型的な特徴は、思いと表情が連動しにくいことです。声を出して笑うことはあっても顔の筋肉があまり動かないことがあります。
悲しみや驚きといった思いも、顔つきに大きな変化として現れにくいため、周囲からは心情が読み取りづらいという印象を持たれがちです。
人見知り・内向的

人見知りが強かったり、内向的であったりする人も、顔に思いが現れにくい傾向にあります。新しい環境や初対面の人と接する際、緊張や不安から顔の筋肉がこわばり、自然な笑顔が出にくくなるのです。
どう思われるかを気にしすぎるあまり、無意識に表情を抑え込んでしまうケースも少なくありません。しかし、控えめで内向的な方は、心を許せる家族や友人の前では表情が豊かになるケースも多くあります。
自分に自信がない
自分自身に自信が持てないことも、表情の乏しさの一因です。自分の表情や振る舞いがどのように見えているかを過剰に意識し、ぎこちなくならないようにと、かえって表情を抑制してしまいます。
過去に心情を表に出してからかわれたり、否定されたりした経験がトラウマとなり、自己防衛のために無表情を装うようになることもあります。
いつも冷静沈着
顔に感情がない人は、周囲から冷静や落ち着いているなどの印象を持たれることもあります。急なトラブルや予期せぬ出来事に対しても、動じることなく冷静に対処できる人が多く、頭の回転が速いケースもあるでしょう。表情がないと聞くとマイナスな印象を抱きやすいですが、周囲の思いに流されず論理的に物事を考えることが得意な傾向があります。
周囲を警戒している

過去に人間関係で嫌な経験をしたり、傷ついたりしたことがある場合、自己防衛のために心情を隠し、周囲を警戒するようになります。大きなリアクションを見せないことで、相手に本心を知られないようにしているのです。
このような人は、心を開くまでに時間がかかりますが、一度信頼関係を築けると、少しずつリアクションが豊かになることもあります。
「表情のない人」になる原因
表情がない状態は、1つの理由だけで起こるわけではありません。様々な原因が複合的に絡み合っている場合が多く、背景には心理的な要因、生まれ持った気質、そして身体的な理由などが考えられます。
ここでは、表情のない人になる原因を4つ紹介します。
心理的な要因

顔に感情がでない人になる原因の1つに心理的な要因があげられます。場の状況や、特定の相手との関係性の中で、心理的な影響を受けて表に出す心情のない状態になっている可能性もあるでしょう。
例えば、話題や目の前の出来事に興味がないと自然と心情が動かず、リアクションも乏しくなります。苦手な相手との会話や人前での発表など、緊張や責任を感じると、顔の筋肉がこわばり、顔つきが硬くなるケースも少なくありません。
性格や気質
性格や気質も、表情に大きく影響します。内向的な人は、自分の内側で心情を感じることが得意な一方、心情を表現することが得意ではないため外見には表れにくいのです。
また、心情の起伏が穏やかで物静かな人もあまり顔つきに変化がない可能性があります。育った家庭環境や文化によって、心情を強く表に出さないことを美徳と教えられた場合無表情につながることがあるでしょう。
病気や障害

表情の乏しさが、特定の病気や障害のサインとして現れるケースも少なくありません。例えば、発達障害を持つ方の中には、非言語コミュニケーションが独特なため表現が難しい傾向にあります。
うつ病やパーキンソン病といった精神的・神経的な疾患が原因で感情が平坦になったり、顔の筋肉の動きが悪くなったりすることで、表情が乏しくなるケースもあるでしょう。
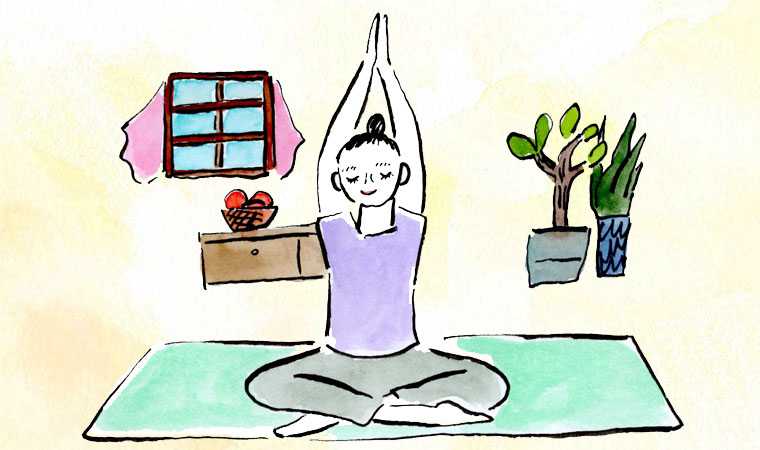
神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。…
表情筋の衰え
顔の表情を作るための筋肉である表情筋が衰えると、表情が上手く作れなくなるケースもあります。表情筋は身体の他の筋肉と同様に、使わないと衰えてしまいます。
長時間マスクをつけていたり、対面でのコミュニケーションが少なかったりすると、口元や頬の筋肉を大きく動かす機会が減り、表情筋が衰える原因となるのです。加齢によっても表情筋は衰えるため、普段から意識して動かしていないと無表情になりやすい傾向があります。
何を考えているの?「表情のない人」の心理
表情のない人は「何を考えているのだろう」「怒っているかもしれない」など表情が読めず、コミュニケーションに影響を与えるケースも少なくありません。
ここでは、表情のない人の心理を詳しく見ていきましょう。
自分の感情を隠したい

表情のない人は、自分の感情を周囲に知られたくないと考えている場合があります。過去に感情を表に出して傷ついたり、弱みを見せたくないという自己防衛の心理が働いているケースも少なくありません。
特にビジネスの場では、感情をコントロールすることがプロフェッショナルであると考える人も一定数います。無表情でいることで、常に冷静で落ち着いた人物であるという印象を与え、自分を守ろうとするのです。
周囲と距離を置きたい

対人関係に苦手意識を持っていたり、人付き合いに疲れていたりする場合、無表情でいることで周囲と心理的な距離を置こうとすることがあります。話しかけづらい雰囲気を作ることで、煩わしい人間関係から身を守ろうとするのです。
このケースは必ずしも相手を拒絶しているわけではなく、自分のペースや心の平穏を保つための無意識の行動である場合が多いと考えられます。
感情表現の方法がわからない
感情そのものは豊かに感じていても、表情として外に出す方法がわからない人もいます。幼少期に感情を表現する機会が少なかったり、感情を表現することを否定されたりした経験がある場合、大人になってから自然な表情を作ることが難しくなることも少なくありません。
心の許せる人と関わったり、社交的になるきっかけがあったりすると、感情表現の方法がわかり、喜怒哀楽が豊かに見えるケースもあります。
表情を意識する余裕がない

仕事や趣味など何かに集中しているときや、精神的に疲れているときは、表情を意識する余裕がなくなりやすいでしょう。特に真面目な人は、目の前のタスクに没頭するあまり、無表情になってしまうことがよくあります。
物事に没頭していない状態や日常会話では、表情が豊かなケースもあるため、一概に表情のない人と判断するのは難しいといえます。
会話や状況がつまらない
会話の内容や場の雰囲気に興味が持てないと、感情が動かないため自然と無表情になってしまう場合があります。このケースは悪意があるわけではなく、正直な反応の表れです。
相手が無表情だと気づいた場合は、興味を引く話題に変えたり、話を中断したりする方が、かえって相手との関係を円滑にできる場合があります。
関係ないことを考えている。

常に自分の世界に入り込んでいたり、ぼんやりと他のことを考えていたりする人も、無表情になりがちです。周囲の会話や出来事から意識が離れているため、話しかけられても反応が薄かったり、無表情でいたりすることがあります。
目の前の状況に関心がないのではなく、単に自分の思考に集中している状態です。無理に関心を引いたり注意したりせず、そっとしておくのがおすすめです。
「表情のない人」が表情を豊かにするための改善方法
表情が乏しいことで悩んでいる人も少なくありません。しかし、いくつかの方法を実践することで、表情を豊かにしてより円滑なコミュニケーションを取ることが可能です。
ここでは、無表情を改善するための具体的な方法を紹介します。自分に合った方法を見つけて、少しずつ試してみましょう。
表情筋トレーニング

表情筋は、顔の表情を作るための筋肉です。日常的に使わないと衰えてしまうため、意識的に動かすトレーニングが効果的です。例えば、「あいうえお体操」は、口を大きく動かすことで、顔全体の筋肉を刺激できます。「あいうえお」とゆっくり大きく発声しながら、顔の筋肉を動かしてみましょう。
また、鏡を見ながら笑顔を作る練習も有効です。口角をしっかりと上げ、目の周りの筋肉も意識して動かすことで、自然な笑顔が作りやすくなります。
感情を表現する練習
感情を言葉だけでなく、表情で表現する練習も重要です。日々の出来事に対して、「嬉しい」「面白い」「悲しい」といった感情を意識的に出してみましょう。好きな映画や本を観た後に、感想を書き出したり友人に話したりしてみてください。ポイントは、自身の感情が相手に伝わるよう話すことです。
また、友人や家族との会話の中で、意識的にリアクションを大きくしてみるのも効果的です。最初はぎこちなくても、繰り返すことで感情と表情が自然に結びつくようになり、徐々に豊かな表現力が身につきます。
専門家へ相談

表情の乏しさが、うつ病や発達障害、失感情症などの病気や障害によるものである可能性も考えられます。もし、自己肯定感の低下や対人関係の困難さといった問題が伴う場合は、一人で悩まずに専門家へ相談することを推奨します。
心療内科や精神科、カウンセラーは、心の状態を客観的に診断し、適切なアドバイスや治療法を提案してくれるでしょう。

「どうせ私なんて……」のネガティブな感情がハッピーな気持ちに切り替わる、精神科医Tomyさ…
「表情のない人」との上手な接し方
表情が乏しい人とのコミュニケーションは、一見難しく感じることがありますが、相手の心理や特性を理解することで、円滑な人間関係を築くことができます。
ここでは、表情のない人との上手な接し方を見ていきましょう。
相手を無理に変えようとしない
表情のない人と関わる際は、無表情である点を指摘したり無理に変えさせたりしないよう意識しましょう。「もっと笑ってよ」「どうして無表情なの?」などの言葉は、相手にプレッシャーを与え、かえって心を閉ざす原因になりかねません。
表情が乏しいことは、人の個性や状態の一部分であり、無理に変えようとしないことが最も大切です。まずはありのままの相手を受け入れ、否定的な感情を抱かないように心がけましょう。相手のペースを尊重することで、自然な関係性を築くことができます。
安心できる雰囲気・環境をつくる

表情のない人は、緊張や警戒心から無表情になっている場合があるため、安心できる雰囲気や環境を作りましょう。騒がしい場所を避けたり、一対一でゆっくりと話したりする機会を設けるのが効果的です。
また、相手の趣味や興味のある話題からゆっくりと関係を深めていくと、徐々に心の壁が取り払われて表情が豊かになることもあります。
言葉でのコミュニケーションを心がける
表情からの情報が少ない分、言葉でのコミュニケーションをより丁寧に行うことも表情のない人と関わるうえで大切なポイントです。相手の意見や気持ちをしっかりと聞く姿勢を見せ、共感の言葉を伝えたり「〜ということですね?」と確認したりすると良いでしょう。
また、自分の感情や考えを言葉で伝えることも大切です。お互いに言葉で補い合うことで、誤解を防ぎ、より深く理解し合うことができます。
表情以外のサインに注目する
表情がなくても、言葉の抑揚や声のトーン、身振り手振りなど、非言語的な部分に感情や意図が表れている可能性もあります。例えば、声のトーンが少しだけ高い場合は楽しんでいるのか、話しているときに頷きが強ければ興味を持っているのかなど考えながらコミュニケーションを取ってみましょう。
表情以外の小さな変化に気づき、注意を払うことで、相手の気持ちをより正確に読み取ることが可能になります。
まとめ

表情のない人は、感情表現が苦手だったり内向的な性格だったりすることから表情が乏しくなっている可能性があります。人によっては、パーキンソン病やうつ病などの病気が原因で表情が乏しいケースもあるため、無理に表情を引き出したり指摘したりするのは控えましょう。
また、表情のない人と関わる際は言葉以外のやり取りにも気を配り、身振りや声のトーンなどから感情を読み取るなど工夫するのがおすすめです。
[ 監修者 ]