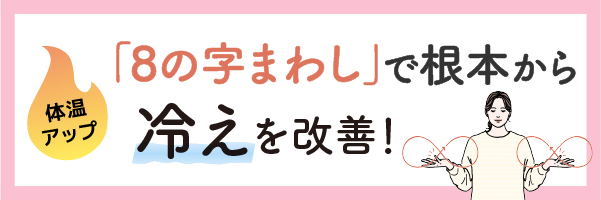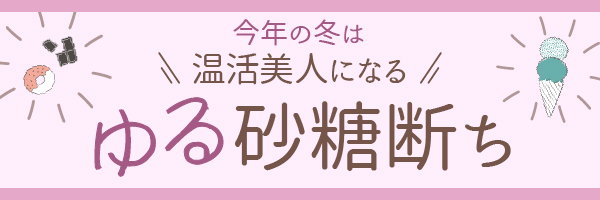夏の「寒暖差疲労」対策|気象病ドクター久手堅司先生の連載
気象病ドクター・久手堅司先生による連載。今回は、気温の寒暖差に体が対応できずに起こる「寒暖差疲労」について。快適な室内の温度・湿度の設定と、自律神経神経を整えることで不調を軽減できますよ。
目次
「寒暖差疲労」と自律神経は深く関わっている
ものすごく暑い室内から、キンキンに冷えた室内へ。その時は快適ですが、実はこうした繰り返しが、あなたを疲れさせているのかもしれません。寒暖差疲労は気象病のひとつで、気温の差が大きくなることにより自律神経が乱れ、疲労が蓄積した状態を指します。
自律神経は、変化する外の環境から、体温や血圧などを一定に保とうとする機能があります。例えば、体温が高くなったら、体温を下げるために汗が出ます。この自律神経の働きで、外が暑い、寒いに関わらず、体温は約36℃程度に保たれているのです。しかし、急激な気温変化が起こると、体温調整がうまくいかなくなり、体が寒暖差に適応しきれずに寒暖差疲労を引き起こしやすくなります。
寒暖差7℃以上で体調を崩しやすくなる

寒暖差には、朝と夜の気温の差や室内外での気温差などがあり、特に、気温差7℃以上の寒暖差の大きい環境、服装を変えなければいけないほどの気温差があるときは、疲労感や不調が出やすくなります。
冷房の使用で室内外の気温差が大きくなる夏は、寒暖差疲労が発生しやすい季節。冷房の効いた部屋から暑い屋外に出て、また冷房の効いた電車に乗る、といったことを1日に何回も繰り返しますと、体内の温度調整を司る自律神経に負担がかかり、エネルギーを消耗し、疲労が蓄積。疲労感の他にも、頭痛や肩コリ、めまい、倦怠感、不眠、食欲不振、便秘や下痢、冷え、むくみ、イライラ、気分の落ち込みなど、さまざまな症状が現れることがあります。
その不調、寒暖差疲労かも?セルフチェックで早めに対策を
寒暖差疲労の可能性をチェックしてみましょう。4個以上該当すれば、寒暖差疲労の可能性があります。当てはまる項目が多いほど、自律神経が正常に働きづらい状態となっていると考えられます。症状が続く場合は、医師に相談しましょう。
<寒暖差疲労のチェックリスト>
□暑さも寒さも苦手に感じる
□季節の変わり目に体調を崩しやすい
□温度が変わらない環境に長時間いることが多い
□寒い場所から暖かい場所に移動すると、顔がほてりやすい
□エアコンで体調が悪くなりやすい
□代謝が悪く、むくみやすい
□寝付きや寝起きが悪い
□湯船に入って体が温まるまで時間がかかる
□手や足などが冷たく感じることがある
□パソコンやスマホの使用時間が1日3時間以上
□肩コリ、首コリがある
冷房を浴び続けて手足の冷えやしびれ感が出るように
寒暖差疲労は、正式な病名ではありませんが、暑い場所とエアコンの効いた涼しい場所を何回も行き来する夏は、心身の不調を訴える人が増えます。寒暖差疲労の中でも、特に冷えがつらくなることが問題。エアコンの冷気で体調不良が続き「寒暖差疲労外来」を受診する人も珍しくありません。

【実録】冷房によるしびれ感、不調が改善
50代でオフィスワークをしている女性。春に配属先が変更になり、席替えでエアコンの真下になりました。6月からエアコンの風が直接あたることになり、左半身にしびれが出てきました。
冷房で不調になったという自覚があったため、厚着をしたりマッサージをしたものの、なかなか改善されず、しびれ感だけでなく、胃腸の不調、肩コリ、頭痛といった症状も現れるほど悪化し、寒暖差疲労外来を受診。
職場の環境を変えることは難しくても、定期的に席から立ち上がって体を動かすことで血流改善によるしびれの緩和が期待でき、足先も冷えにくくなります。冷たい物の摂りすぎにも注意が必要です。
また、夏でもシャワーで済ませず入浴で体を温めるなどの生活習慣の改善によって、徐々に快方に向かっています。
快適な室内環境と自律神経を整えるケアを
猛暑の影響で熱中症予防のために、1日中冷房の中にいることも多くなっています。
寒暖差疲労だけでなく、エアコンの風にあたることで体が冷えてしまうと、他の不調も連動して起こりやすくなります。また、一度寒暖差疲労になると、自律神経が酷使され、他の人は平気な環境でも不調を訴えるようになることがあります。そもそも、不規則な生活などで自律神経の乱れている方は、体温調節ができず熱中症になるリスクも高まります。日頃から自律神経を整えて、寒暖差に負けない体質作りを心がけましよう。
室温は25~28℃、湿度は50%程度がベスト

寒暖差疲労対策には、エアコンの設定温度を調整して、適切な室温をキープすることが重要です。
快適な室温は25~28℃、湿度は50%程度が理想的で、自律神経の安定にもつながります。気温だけでなく、湿度が高いと熱中症の危険度や不快指数も上がるので注意しましよう。
ぬるま湯で首まで浸かる
入浴の健康効果は幅広く、温熱作用による血流促進、冷え改善、自律神経の調整、睡眠の質の向上などさまざまな効果があります。手軽でおすすめの入浴法は、38~41℃程度の湯船に約10~15分、首までしっかり浸かること。全身をまんべんなく温めることができ、慢性的な冷えも防ぎ、自律神経も整いやすくなります。汗をかきやすい体質作りにも役立ちます。
生活リズムを見直し睡眠の質を高める
寒暖差疲労の症状として、睡眠トラブルがあります。自律神経の乱れにより、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかないと、寝付きが悪くなったり夜中に目が覚めたりすることが増えます。
不規則な生活を見直し、7~8時間の睡眠時間を確保する、寝室の温度を適切に調整する、寝る前はスマホを控えるなどの工夫を。良質な睡眠は自律神経のバランスを整え、心身の回復を促します。
暑さに体を慣らす「暑熱順化」で体調をキープ

寒暖差疲労の症状が出ている人は、少し汗をかく程度の軽い運動を取り入れてみて。暑さに体を慣らすことを意味する「暑熱順化(しょねつじゅんか)」で汗をかきやすくなり、体温調整がスムーズになります。寒暖差疲労対策や熱中症予防にも効果的です。ウォーキングなら30分、ジョギングなら15~20分ほどの汗ばむ程度の負荷でOKです。朝夕の涼しい時間帯に取り入れると継続しやすいでしょう。1~2週間程度かかりますが、徐々に体が慣れていくことで自律神経が安定すれば、体調の良い日がずっと続きますよ。
イラスト/Aikoberry

きびしい猛暑で、毎日寝苦しい夜が続きます。そこで要注意なのが、寝ている間に起こる熱中症です…

曇っていたり室温がそんなに高くなくても熱中症になる人があとをたちません。どうしてだろう? …

熱中症は、子どもやお年寄りだけでなく、条件次第でどの世代でもかかる危険性があります。「体力…
[ 監修者 ]