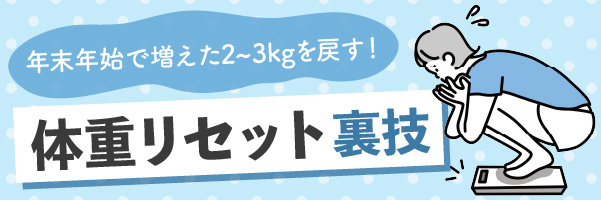体臭がきつい女性の特徴と原因は?汗臭や加齢臭を改善・予防する方法
体臭の悩みは、なかなか人に相談しにくいもの。実は、体臭がきつい女性の特徴にはいくつかのパターンがあります。女性の体臭が強くなる特徴や原因、そして改善・予防するための対策を知っておきましょう。
目次
女性の体臭が強くなる特徴と種類

女性の体臭には、年齢や生活習慣によって異なる特徴が見られます。
10~20代の若い女性からは「ラクトン」と呼ばれる物質が放出されており、特有の良い香りを放つと言われます。しかし、ラクトンは加齢とともに減少。「ミドル脂臭」「加齢臭」のほか、さまざまな臭いが気になるようになっていきます。
体臭対策を考えるうえで、まずは自分の体臭がどの種類に当てはまるのかを知ることから始めてみて。
40代以降で気になりやすい「ミドル脂臭」

「ミドル脂臭」は、主に30代半ばから50代半ばにかけて気になりやすい体臭です。
“使い古した油のような臭い”と言われるミドル脂臭は、汗に含まれる乳酸が皮膚の常在菌によって分解される際に作られる物質「ジアセチル」が、皮膚の「中鎖脂肪酸」と混じることで生じます。
働き盛りでストレスなどにより交感神経が優位になりやすい30〜50代では汗に含まれる乳酸が増えやすく、ミドル脂臭が発生しやすくなります。発生しやすい部位は、頭皮や首の後ろ、耳のまわりなどです。
ジアセチルは少量でも強く臭いを放つうえに、空気中に広がりやすいという厄介な特徴を持っています。そのため、気になりやすい臭いの1つです。
女性の場合、更年期症状の「ホットフラッシュ」がミドル脂臭の原因になることも。皮脂や乳酸などを含んだ汗を大量にかくことで、臭いの悩みにつながる場合があります。
更年期以降に起こりやすい「加齢臭」

もう1つ、年齢を重ねるにつれて悩む人が増えるのが「加齢臭」です。男女ともに40代後半ごろから気になり始めますが、女性の場合、特に更年期以降に強くなる傾向が見られます。
加齢臭の原因は「ノネナール」という物質。皮脂に含まれる特定の脂肪酸が酸化すると生成される物質で、油っぽい臭いに加えて、“枯れ草のよう”と言われる独特な臭いを引き起こします。
更年期に差し掛かり、女性ホルモンが減少すると、相対的に男性ホルモンの働きが優位になります。すると皮脂の分泌量が増え、酸化も進みやすくなるため、加齢臭が発生しやすくなると言われます。
「ベタベタとした汗」の臭い

汗は体温を調整するうえで欠かせない存在ですが、気になる臭いを引き起こすことも。特に「ベタベタとした汗」は、体臭の原因として知られています。
汗はそもそも、血液がろ過されて作られており、次の2種類があります。
- サラサラ汗:かいた後にすっきりとする。蒸発しやすく乾きやすい、臭いも少ない
- ベタベタ汗:かいた後に不快に感じる。蒸発しにくく乾きにくい、臭いが強い
この2種類の汗の違いは、汗腺の機能によるものです。サラサラ汗は、汗腺を通って出てくるときにしっかりとろ過されており、ほぼ“水”に近い状態。一方、ろ過しきれていないのがベタベタ汗で、余分なミネラルなどが多く含まれてしまっています。こうした物質が雑菌によって分解され、臭いの原因となるのです。
加齢や運動不足、エアコンの効いた環境で過ごす時間が長いなど、普段から汗をかかない習慣が続くと汗腺の機能が低下しやすくなります。汗のケアをこまめに行うほか、生活のなかで汗腺の機能を鍛えることが対策につながります。

日頃の疲れをしっかり取り除き、心と体を癒やすためのヒントが大集結!体が喜ぶ入浴法や食事など…
「わきが」による臭い

「わきが」は、アポクリン汗腺から分泌される汗が皮膚の常在菌によって分解されることで発生する特有の臭いです。
アポクリン汗腺は、脇の下や乳首、デリケートゾーンなど特定の部位に分布しています。ここから出る汗は、タンパク質や脂質など、臭いの原因となる成分を多く含んでいるのが特徴です。かいたばかりの汗そのものは無臭ですが、皮膚表面の常在菌が原因物質を分解することで、特有のツンとした臭いにつながってしまいます。
アポクリン汗腺が多い人・活発に動く人では汗の量も増え、臭いが強くなりがちに。思春期以降のホルモンの影響のほか、遺伝的な要素も関係していると言われています。
脂っこい料理・肉料理中心の食生活による臭い

体臭がきつい女性の特徴として、食生活の偏りも関係している場合があります。脂っこい料理や肉料理を中心とした食生活を送っていると、体臭が強くなる可能性が考えられます。
肉類に多く含まれる動物性脂肪やタンパク質は、腸内で悪玉菌のエサとなりやすいもの。分解される過程で、臭いの元となる物質が発生することがあります。こうした原因物質が血液に溶け込み、全身を巡って汗や皮膚ガスとして排出される際に、不快な体臭につながることがあるのです。さらには、便やおならの臭いを強くする場合もあります。
揚げ物などに含まれる油も、体内で酸化して体臭の原因となることがあります。体臭の予防や改善を意識するなら、バランスの取れた食事を心がけて。
多忙やストレスによる「疲労臭」

疲労やストレスが原因となって、体臭が強くなることも。「疲労臭」は、体に疲れがたまると発生すると言われている体臭で、ツンとしたアンモニアのような臭いが特徴です。
消化の過程で、私たちの体内ではアンモニアが発生します。通常、アンモニアは肝臓で分解されますが、疲労やストレスがたまると肝臓の働きが低下。アンモニアを十分に分解できなくなります。分解されずに残ったアンモニアは血液に乗って全身を巡り、ガスとして皮膚から発生することがあり、これが疲労臭となります。
汗の臭いとは異なり、血液からしみ出すガスの臭いなので、入浴などでは消せないのが疲労臭の特徴。ゆっくりと休息をとる、ストレスを適切に解消するといった根本的な対策が欠かせません。
便秘が続くと悪玉菌も臭いのもとに
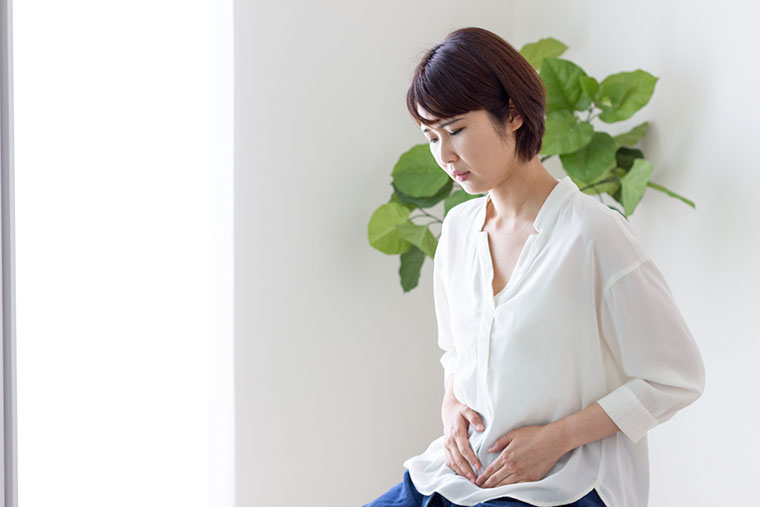
便秘が長く続くと、腸内にたまった便が腐敗し、悪玉菌が増殖。腐敗臭をともなう有害物質やガスが発生しやすくなります。この有害物質が腸壁から吸収されて血液に溶け込み、全身を巡って汗や皮膚から排出されると、体臭として感じられる場合があります。さらには、口から排出されて「口臭」になることも。
腸内環境が悪化することで起こるトラブルは、体臭だけにとどまりません。肌荒れや免疫力の低下を引き起こすおそれもあるので、便秘を解消し、腸内環境を整えることは体調管理のうえでも必須。善玉菌を増やすような食生活を心がけるのもおすすめです。
体臭が病気と関連していることも
体臭の変化は、健康状態を知る手がかりの1つ。ときには、体の不調や病気のサインとして臭いが現れるケースがあります。
たとえば糖尿病になると甘酸っぱい臭い、肝機能や腎機能が低下している場合にはアンモニア臭が体から感じられることがあります。ほかにも、特定の皮膚疾患や代謝系の病気が体臭の原因となるケースも見られます。
普段と明らかに違う体臭が続く場合や、体臭以外にも体調の変化を感じる場合は、医療機関を受診しましょう。
自分の体臭をセルフチェックする方法

人の嗅覚は、同じ臭いをかぎ続けると慣れてしまい、その臭いを感じにくくなります。そのため、自分の体臭には意外と気づきにくいもの。ここまで紹介してきた特徴に当てはまる場合は、もしかしたら注意が必要かもしれません。
自身の体調をセルフチェックしたいなら、たとえば次のような方法を試してみて。
- 清潔なタオルやガーゼで、耳の後ろや首すじ・脇の下などを拭き取り、かいでみる
- 脱いだ衣類(特に肌着やパジャマ)の臭いをかいでみる
- 枕カバーの臭いをチェックする
体臭を軽減するための対策
体臭を改善したいなら、原因に合わせたさまざまな対策を組み合わせることが効果的。生活習慣の見直しや食生活の改善、適切なボディケアまで、できることから始めてみましょう。
汗を適切にケアする

体臭対策の基本は、汗を適切にケアすることです。かいた直後の汗は無臭でも、そのままにしておくと、皮膚の常在菌が繁殖して臭いの原因物質を作り出してしまいます。
かいた汗が臭うようになるまで、1時間程度かかると言われています。汗をかいたら、清潔なタオルや汗拭きシートでこまめに拭き取るようにしましょう。特に脇の下や首元、背中など、汗をかきやすい部分は念入りに拭くことを心がけて。
市販の制汗剤やデオドラントアイテムを使うのもOK。ただし制汗剤のなかには、汗腺をふさぐことで汗の量を減らすものも。広範囲に使いすぎたり、長時間使用したりするよりは、気になる部分に限定して使用するのが良いでしょう。
通気性の良い服を着る
着るものに配慮することも、体臭を軽減できる対策の1つ。汗が衣類に染み込むと雑菌が繁殖しやすくなるため、通気性が良く、乾きやすい素材の服を選びましょう。綿や麻といった天然素材は、吸湿性も高いためおすすめです。脇汗パッドなどを使うのも◎。
化学繊維にも、速乾性や通気性に特化されたものがあります。スポーツウェアなどを選ぶときにはぜひチェックしてみて。
汗による蒸れや臭いを防ぎたいなら、服の形も気をつけたいところ。締め付けの強いタイトな服よりも、ゆったりとしたシルエットの服を選べば、蒸れを予防できます。重ね着をする場合は、肌に近いインナーに通気性の良い素材を選ぶと効果的です。
抗酸化食品を食べる

加齢臭の原因の1つに、体内で発生する活性酸素による「脂質の酸化」が挙げられます。この酸化を抑えるのに役立つのが「抗酸化食品」です。
ビタミンCやビタミンE、ポリフェノールなどを含む食品を積極的に食事に取り入れれば、間接的な体臭対策につながります。抗酸化作用が強い食品には次のようなものがあります。
- ベリー類
- 柑橘類
- 緑黄色野菜
- ナッツ類
- 緑茶
- 大豆製品 など
バランス良く摂取すれば、体の内側から酸化を防ぐことができ、体臭の原因物質ができにくい体づくりをサポートできます。
反対に、脂質が多いスナック菓子や揚げ物、ファストフードなどは控えるのがベター。また、肉類を多く食べている人で臭いが気になる場合は、肉の量を少し減らすと良いでしょう。
適度な運動を行う

適度な運動は、体臭を軽減するために有効な対策の1つです。
普段あまり汗をかかない人ほど、汗腺の機能が低下しがち。臭いの原因となり得るミネラルなどを多く含んだ「ベタベタ汗」をかきやすくなります。
運動で良い汗をかく習慣がつけば、汗腺の機能が向上。蒸発しやすい「サラサラとした汗」をかけるように。ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなど、無理なく続けられる有酸素運動を取り入れてみましょう。
運動で体を動かせばストレス解消にもつながるため、疲労臭の対策にも役立ちます。ただし、激しい運動はかえって活性酸素を増やしてしまう可能性もあるので、無理のない範囲で行いましょう。

40代・50代は、ホルモンバランスの乱れで髪の状態も不安定になりがち。パサつきを押さえたツ…
入浴時の習慣を変える
毎日の入浴は、臭い対策を行ううえでとても大切な習慣の1つ。臭いの原因となる汗や皮脂を落とすほかに、汗腺の機能を向上させることにもつながります。
気になる部分の皮脂や垢を落とす
体を清潔に保てば、臭いの原因となる雑菌の繁殖を抑えられます。特に脇の下や足の指の間、ひじ・ひざの裏などは汗がたまりやすいため、意識的に洗うことをおすすめします。ただし、ナイロンタオルなどでゴシゴシ洗いすぎるのは避け、石けんやボディソープをよく泡立てて優しく洗いましょう。
すすぎ残しも臭いの元となる場合があるので、しっかりと洗い流すことも忘れずに。
湯船に浸かって汗をかく

シャワーだけでなく湯船にゆっくり浸かると、汗腺の機能を高め、気持ちよく汗をかくことができるように。
入浴前にコップ1杯の水を飲んだら、38~40度程度のお湯に肩までしっかり、10分程度浸かりましょう。お湯が熱すぎると、体の芯まで温まる前に湯船から上がりたくなってしまうので、「少しぬるいかな」と感じる程度がベストです。
入浴後、水分を拭き取った後は、すぐに冷房の風に当たると汗腺が閉じてしまいます。うちわや扇風機の優しい風を当てる程度にとどめ、自然に体温を下げると良いでしょう。
質の良い睡眠をとる
体臭、特に疲労臭には睡眠の質が深く関わっています。
睡眠不足や質の悪い睡眠が続くと、体の疲れやストレスが回復しにくくなります。すると体臭の原因となるアンモニアなどの物質が体にたまりやすくなってしまうと言われています。
寝る前はカフェインの摂取を控える、スマートフォンやパソコンの画面を見ないようにするなどの小さな習慣が、スムーズな入眠と質の良い睡眠につながります。軽いストレッチをはじめ、リラックスできる習慣を取り入れるのもおすすめです。
規則正しい生活リズムで十分に睡眠をとり、体の回復を促しましょう。
ストレスを解消する

ストレスは、疲労臭や加齢臭を強める要因の1つです。ストレスがたまると自律神経のバランスが乱れ、体の機能に影響が出ることがあります。
趣味に没頭する、友人とおしゃべりをする、アロマセラピーを取り入れるなど、自分に合ったストレス解消法を見つけ、意識的にリラックスする時間を作りましょう。深呼吸や瞑想もストレスの緩和に役立ちます。
多忙な毎日を過ごしている人は、1日にほんの少しで良いので「自分のためだけの時間」を作ってみると、ストレスが原因の臭いの軽減につながるかもしれません。
原因に合わせた対策で快適な毎日に!

女性の体臭が気になる場合、その原因は1つとは限りません。汗の種類や量、年齢による体の変化、食生活や生活習慣の乱れ、ストレス、そして場合によっては病気が関連していることもあります。体臭がきつい女性の特徴を知り、状態に合わせた適切な対策を行いましょう。
紹介したセルフチェックや、汗や食生活、運動、睡眠、ストレスケアといったさまざまな対策を参考に、できることから日々の生活に取り入れてみて。もしセルフケアで改善が見られない場合や、気になる症状がある場合は、医療機関に相談することも選択肢の1つです。
体臭の悩みを抱え込まず、より快適な毎日を過ごすための一助としてくださいね。
[ 監修者 ]