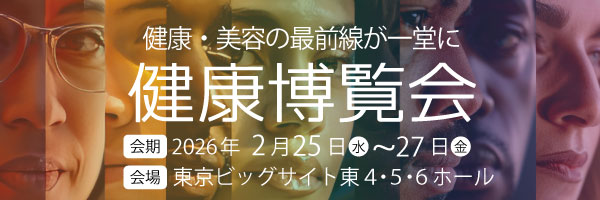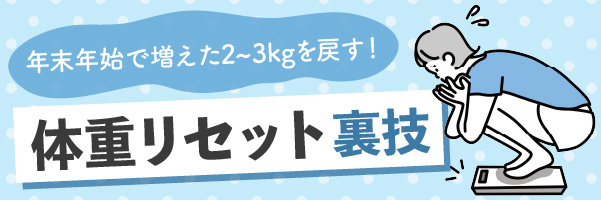冬に気分が落ち込む「冬季うつ」対策|気象病ドクター久手堅司先生の連載
気象病ドクター・久手堅司先生による連載。冬になると天候は曇りがちになり、なんとなく気分も沈むことが増えていませんか?そこで今回は、「冬季うつ」対策につながる、幸せチャージ法をお届けします。
目次
寒くなると気分が落ち込むのは“光不足”が原因
本格的な寒さが始まるこの季節。寒いとつい家にこもりがちになり、気づけば外に出る時間や日光に当たる時間が少なくなっていませんか。冷たい風と曇り空に、なんとなく気分が沈む日もありますよね。
日照時間が減ると、“幸せホルモン”とも呼ばれる「セロトニン」の分泌が減り、気分が落ち込みがちになります。セロトニンは心の安定や快眠、食欲のコントロールなどに深く関わっており、光刺激が足りなくなると、脳内でセロトニンの合成が低下するため、心身のバランスが崩れやすくなるのです。
さらに、セロトニンから生成される“睡眠ホルモン”「メラトニン」のリズムも乱れてしまうため、眠りの質が下がり、朝すっきり目覚めにくくなることも。
その結果、気分の落ち込みや眠気、体のだるさ、過食傾向が現れる場合もあります。
「冬季うつ」と気象病が重なると不調が強くなる

実は、光不足による無気力やイライラなどの変化は「冬季うつ」と呼ばれ、秋から冬にかけて悪化し、春に回復する季節性の不調です。「季節性感情障害(SAD)」とも言われ、男性より女性に多く見られるのが特徴。気がつかないうちに心の元気が少なくなり、やる気が出にくくなる人も少なくありません。
さらに、冬季うつに、低気圧や寒暖差といった環境ストレスが重なることで、自律神経のバランスが乱れ、だるさや気分の落ち込みが強まることも。冬季うつと気象病は切り離せず、互いの不調が重なって症状が強まりやすい傾向があります。
気圧や寒暖差の影響を受ける気象病とも、深く関わっています。
天気によるメンタル不調チェックリスト
季節の変化は、心や体にさまざまな不調となってあらわれます。「冬季うつ」の代表的なサインもチェックし、自分の気分や体の変化に気づいてあげましょう。

□いつも体が重だるく、やる気がわかない
□気分が落ち込みやすい
□イライラや不安感が続いて、日常生活に集中できない
□寝ても寝ても眠い、日中に眠気を感じる
□朝起きるのがつらい
□食欲が増して体重が増えた
□「うつ病かもしれない」と思ったことがある
チェック項目に3つ以上当てはまる場合は、天気の影響によるメンタルの不調の可能性が。特に、「食欲が増して体重が増えた」あるいは、「寝ても寝ても眠い、日中に眠気を感じる」に該当する場合は、冬季うつのサインかもしれません。
症状が2週間以上続く場合は、医療機関に相談することをおすすめします。
冬の落ち込みと止まらない食欲
11月に入ると、冬季うつの症状を感じる人がぐっと増えてきます。気力が低下したり、冬場に気分が変化するのは自然なこと。自分を責めずに受け止めながら、気象の変化に合わせたセルフケアを取り入れることが改善のポイントです。

【実録】セルフケアで2年続いた冬季うつを克服
冬季うつの症状が2年間ほど続いていた20代の女性のケースです。冬になると気分がふさぎがちになり、仕事に行きたくなくなったり、食欲が増したりなど、冬季うつの典型的な症状が出ていました。いきなり薬に頼るのではなく、まずは生活習慣を中心に日常生活でのセルフケアから改善できるようにサポート。
例えば、朝起きたら太陽の光を浴び、少し体を動かすことを数カ月続けたところ、自然と症状が軽くなりました。さらに、寒暖差による冷えや倦怠感、頭痛、肩コリといった気象病を予防することも、季節性のメンタル不調に負けない体づくりにつながります。
冬の落ち込みをやさしく整える3つのキーワード
寒さや日照不足で気分が落ち込みやすい冬。おすすめしたい、心を守るキーワードは「好きなこと」「腸活×温活」「良い睡眠」の3つ。がんばるのではなく、できるところから生活リズムを整えてみましょう。
(1)好きなことを日常に取り入れる

趣味や好きなことに夢中になっている時間は、脳内でセロトニンが分泌され、自然と気持ちが前向きになります。
好きなことに没頭する時間を増やすことで、冬に不足しがちなセロトニンを補うことができます。さらに、好きなことをしながらリラックスしている間はストレスホルモンの「コルチゾール」が下がり、自律神経も整いやすくなります。
おうちでも外出先でも、無理をせず「好きなこと」を少しずつ積み重ねてみましょう。お気に入りの動画を観たり、ちょっと寄り道してスイーツを楽しんだり、動物と触れ合ったりするなど、自分の心がほっと温まる時間を少しずつ増やすことが、心と体のめぐりをやさしく整えてくれます。
(2)「腸活×温活」で冬に負けない

寒さが増すこれからの時期こそ意識したいのが、免疫力を支える腸の健康です。最近注目されている「脳腸相関」という言葉を知っていますか?
脳と腸は神経やホルモンを通じて密接にやり取りしており、腸内環境が乱れていると、気分が落ち込みやすくなったり、いつもよりストレスを強く感じてしまうことが分かっています。
腸内環境を整えるには、ヨーグルトや納豆、味噌などの発酵食品を毎日の食卓にコツコツ取り入れるのがおすすめ。さらに、冷えた体を温める「温活」も大切です。生姜や根菜を使ったスープ、湯船でゆっくり温まる習慣で血流を促しましょう。
(3)良い睡眠が心の安定につながる

夜遅くまでSNSや動画を眺めているうちに寝るタイミングを逃してしまう…。寝落ちスマホや「リベンジ夜更かし」で、眠りが浅くなったり就寝時間が遅くなったりすると、自律神経のバランスが乱れ、心身のリズムも崩れやすくなります。冬季うつや気象病で気分が落ち込みやすい人ほど、質のよい睡眠が心の安定を支えるカギになります。
夜更かしを控え、ぬるめのお風呂でゆっくりリラックスしてから眠ることで、自律神経のバランスが整い、腸の動きもスムーズに。睡眠不足は腸にも心にも影響するので、毎日の眠りを大事にしましょう。
イラスト/Aikoberry

気象病ドクター・久手堅司先生による連載。冬になると天候は曇りがちになり、なんとなく気分も沈…

胃腸が弱りやすいこの時期は、暴飲暴食や脂っこいものを控えて胃腸をいたわらないと、さまざまな…
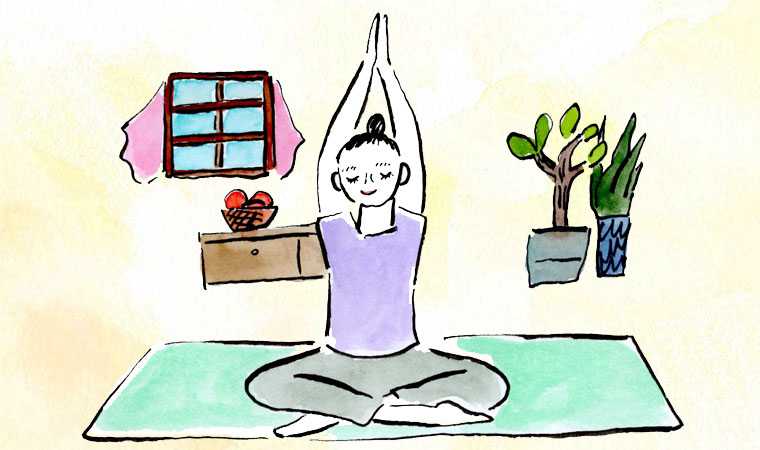
神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。…

体力が続かない、イライラしやすいなど、さまざまな心身の不調は、「気」「血」不足が原因かもし…
[ 監修者 ]